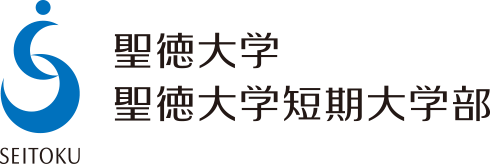小学校 2025年2月(第140号)
【附属小学校】豆太がかけ出した時の気持ちは?ー 国語科授業研究ー
人を助ける行動のスイッチが入る条件。「相手の気持ちを思いやるチカラ」「相手との関係」「内的、外的報酬」「自分のほかに助ける人の有無」「自分のリスクとの天秤」…。
3年生の物語教材に「モチモチの木」があります。夜ひとりでトイレに行けない豆太。そんな「臆病者」の豆太が、夜中に腹痛を訴える「じさま」を助けるため、夜道を下ってふもとの「医者様」を迎えに行く。勇気をふり絞り、無事「じさま」を助けた豆太だが、物語の終末では、夜中にトイレにひとりで行けない様子が再び描かれている。そんな「豆太がかけ出した時の気持ち」は、なんだろう?1月23日(木)、加藤駿学級の3年生が、国語科の授業研究で、白熱した対話を繰り広げました。
子どもたちのワークシートの記述から。
「じさまが、しんでしまう!」(相手の気持ちを思いやるチカラ)
「今までお世話になっていたじさまが、はらいたになったから、今こそ助けなくっちゃ!」(相手との関係)
「豆太もモチモチの木に灯がともるところを見たい」(外的報酬)
「じさまがいなくなると一人でくらさなくてはいけない」(自分のリスクとの天秤)
そして一番のスイッチは、「自分しか助ける人がいない」(自分のほかに助ける人の有無)
子どもたちは、まさに人を助ける行動のスイッチが入る条件を、物語文から読み取っていたのでした。この心理学的な分析は、授業後の協議会で、聖徳大学 児童学科教授の東原文子先生から、ご教示いただいたものです。心理学の切り口で、物語文を読み解く手法が、これからの国語教育発展につながる予感がしました。