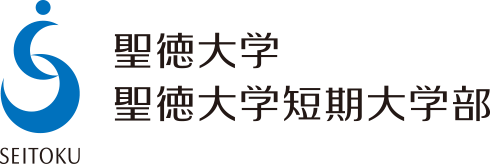言語文化研究所主催によるシンポジウムが、去る3月1日(土)に本学1号館1323教室にて開催されました。これは、研究所のプロジェクト「国際比較言語文化研究」の一環として毎年おこなわれているものです、
パネラーは近藤圭一先生(日本語)、アラン・メドウズ先生(米語)、アダウト・ジニーズ先生(ポルトガル語)、李哲権先生(中国語)、フォー・サミュエル先生(カメルーンの言語)で、私(北村)が司会を務めました。今回のテーマは「巷間に伝わる伝承その由来」ということで、誰もがかかわる日常的なものです。しかし、こうした生活に根差している表現こそが、各々の文化圏の特色を如実に言語に色濃く反映していると言うこともできます。
各先生からは、言語圏の特色に即して「葬送の儀礼」「ポップカルチャーの神話上の生き物」「ブラジルの民間伝書――ボイタタ(大蛇の悪霊)とサシ(鳥の姿の霊)」「西域のドラゴン伝説」など、多岐にわたるテーマが出されました。ここで大切なのは長い間、人々の間で忘れられることなく(無視されることなく)、また、荒唐無稽なものと蔑まれることもなく、むしろ葬り去ってはならぬ民族の営みの証ともなるべき内容でしょう。当日も「龍」などをめぐっては西洋のドラゴンに対して、東洋の龍、大蛇(おろち)などとの違いや、映画「ハリー・ポッター」の逸話も登場しました。
3時間を超えるシンポジウムとなりましたが、熱心な来場者からの感想や質問も出され、大いに興味を抱かせるシンポジウムになったと思います。

(関連記事)
3月1日(土)、聖徳大学言語文化研究所主催シンポジウム「各言語圏別に見た“巷間に伝わる伝承とその由来”」を開催いたします